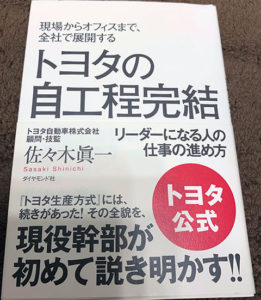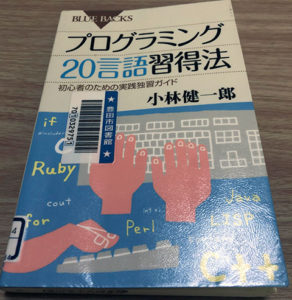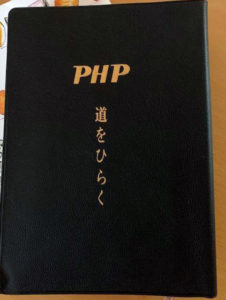国際交流、国際援助の一環として外国人技能実習制度があります。この制度が円滑に利用できるように実習生と企業との橋渡しを行い、サポートする協同組合があります。
長野県でも外国人技能実習生の受け入れが行われていて、これをサポートする協同組合が存在します。
外国人技能実習制度とは?
外国人技能実習制度とは、我が国で培われた技能や技術、知識を開発途上地域へ移転することで、その地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与する目的で創設された制度です。
外国人技能実習生を採用するメリットと注意点とは?
外国人技能実習生を採用するメリットは次の2つです。
・海外進出の戦力になる
外国人の雇用によって、新しい市場の開拓や、海外進出の際にスムーズにビジネス展開ができるでしょう。
・優秀な人材を確保できる
少子化による若手人材が不足する日本において、海外の若い優秀な人材を確保できる点はメリットです。
外国人を採用する際の注意点は次の2つです。
・在留資格を確認する
外国人技能実習生を採用して働いてもらうには、留学ビザから就労ビザへ変更していることを在留カードで確認する必要があります。また、就労ビザには有効期限があるので同時に確認しましょう。
・労働条件を明確にする
言葉やニュアンスの違いによってトラブルが起きないように、労働条件を明確に提示することが大切です。
長野県の外国人技能実習生受入サポート組合を紹介
“長野県の外国人技能実習生受入サポート組合員を2つ紹介します。
・P&F事業協同組合
P&F事業協同組合は、10年に渡って組合員の企業に1500名以上の外国人技能実習生の受け入れを行ってきた企業です。インドネシア、ベトナム、中国、タイとの取引実績があり、経験豊富なスタッフがサポートを行います。
・ジャパンテクノフィールド協同組合
長野県長野市で、企業の外国人技能実習生受け入れをサポートしています。受け入れに当たっては入国前から帰国まで、外国人技能実習生と受け入れ企業の双方に徹底したサポートを行っているので安心して利用することができます。
以上、長野県の外国人技能実習生受入サポート組合を紹介しました。外国人技能実習生の受け入れを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。